医療事務に資格は必要?
医療事務には、実に様々な資格や試験があります。
しかし、医療機関で医療事務として働くためには、実際のところ、資格は必須ではありません。入職してから医療事務の研修を実施する医療機関もあるので、まったく未経験のまま医療事務に就職する方もいます。
ところが、医療事務が担当する診療報酬請求事務は、業務を行う上で専門的な知識が必要とされます。
このような診療報酬請求事務に従事する医療事務の資質の向上を目的に実施されているのが、診療報酬請求事務能力試験です。
診療報酬請求事務能力試験は全国一斉統一試験として実施されます。医療事務関連の資格の中では人気が高く、そしてひと際難しい試験として医療機関からも注目されています。
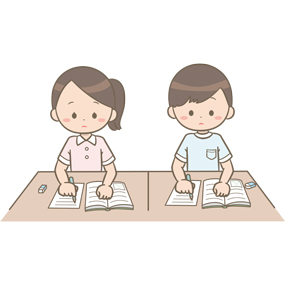
診療報酬請求事務能力試験とは
「診療報酬請求事務能力認定試験」(以下「認定試験」)は,数ある医療事務関連の資格試験のなかで,唯一厚生労働省が認可している資格試験です。
試験ではレセプト作成の実践力を問われます。そのため,診療報酬点数表についてかなり深い知識が要求されます。
認定試験は医療事務の資格試験のなかでは難易度が高い試験です。
その合格率は、28.4%!かなり厳しいですね
本試験は学科問題と実技試験から構成され、それぞれが合格ラインに達することが合格条件になっています。
つまり、学科が満点でも実技が合格ラインに満たない場合は不合格になるので、バランス良く学習していくことが大切です。
診療報酬請求事務能力試験 合格後のメリット

医療事務は、医師や看護師のような国家資格ではないため、診療報酬請求事務能力試験に合格しないと医療事務になれないという決まりがあるわけではありません。
しかし、合格者には大きなメリットがあります。
① 就職に有利
医療機関の求人の中には、診療報酬請求事務能力試験に合格していることを応募条件に加えているところも見受けられます。
即戦力として今すぐ活躍してもらえる人に来てほしいという、医療機関のニーズが高いことがわかりますね。
こういう病院で働きたい、この地域でどうしても働きたいなどの就職先に関する希望がある場合は、診療報酬事務能力認定試験に合格しておくと、希望の就職先が見つかる可能性が高くなります。
② 資格手当が出る(※医療機関によって事情が異なります)
医療機関によっては、診療報酬事務能力認定試験合格の資格手当を支給しているところもあります。
合格後のお給料に資格手当が上乗せされるケースが多いので、早く合格すればそれだけ収入にプラスになります。
※資格手当の有無や支給額は医療機関によって異なります。
③ 本当に使える医療事務の知識が身につく
合格したことで得られるもので一番大きいのは、一人前の医療事務として能力の認定を受けたことです。
これだけ難関な試験を通過した合格者には、診療報酬請求事務に関する知識も実務能力も,十分なレベルのものが身についているはずです。
そして、この合格のために努力した経験こそが、これからの仕事に対する自信を支えてくれます。
診療報酬事務能力認定試験の概要
ここでは診療報酬事務能力認定試験の概要を紹介します。
主催:公益財団法人日本医療保険事務協会 資料の持込み:可
日程:年2回(7月と12月) 受験資格:特になし
試験時間:3時間 受験手数料:9,000円(税込)
構成:学科(20問)と実技(2問) 合否の通知:試験の約2カ月後
出題範囲:「診療報酬請求事務能力認定試験 合格率:約30%
ガイドライン」に従う
試験日時などの詳細は(公財)日本医療保険事務協会のホームページでご確認ください。
URL http://www.shaho.co.jp/iryojimu/
認定試験の出題範囲と攻略法

出題範囲は大きく分けて13項目あります。
- 医療保険制度等
- 公費負担医療制度
- 保険医療機関等
- 療養担当規則等
- 診療報酬等
- 薬価基準・材料価格基準
- 診療報酬請求事務
- DPC
- 医療用語
- 医学の基礎知識
- 薬学の基礎知識
- 医療関係法規
- 介護保険制度
この中からまんべんなく出題されるのではなく、各項目によって出題数の増減があり、試験によっては1問も出題されない時もあります。
まずは出題傾向を分析することが重要です。
詳しい出題傾向はこちらのページでご確認ください。
実際の問題を解いてみよう
認定試験の問題は学科と実技に分かれています。
今回は学科問題について詳しく見ていきたいと思います。
学科の問題は全20問で,1問は(1)~(4)の4つの文からなり,それぞれの正誤を判定したうえで正誤の組合せを示した選択肢「a」~「e」の中から正しいものを選択する形式になっています。
問 次の文章のうち正しいものはどれですか。
(1) 後期高齢者医療制度の一部負担金は病院,診療所ともに定率1割負担(現役並み所得者3割)であり,慢性腎不全などの高額長期疾病患者の上限額は月1万円である。
(2) 保険給付の制限は,被保険者について行われるものであり,被扶養者については行われない。
(3) 後期高齢者医療制度における高額療養費制度においては,現役並み所得者や低所得者については自己負担限度額が一般と別に定められている。
(4) 国保被保険者資格証明書による療養については,医療機関での患者負担金は医療費の全額となる。
a (1),(2) b (2),(3) c (1),(3),(4) d (1)~(4)のすべて e (4)のみ
いかがでしたでしょう?わかりましたか?
■POINT■ 解説
実際に問題を解く際には,点数表などでそれぞれの文章の正誤を判定します。
上記の場合,(1)は正しく,(2)は誤りとなります。
そのことがわかった時点で,正しい選択肢は(1)を含みかつ(2)を含まないもの――すなわち「c」であると断定できます。
このように,すべての文章の正誤を判定しなくとも,選択肢の組合せから正解を導き出すことでよりスピーディな回答が可能になります。
試験は時間との戦いですので,こうしたテクニックも重要になってきます。
初めて問題を解いてみると、少し難しく感じたかもしれません。
しかし、点数表を片手に過去問を解いたり、間違えた問題の解説を見ながら一つ一つ見直していくことで、合格へ一歩ずつ近づいていきます。
次の項目では、学習の目的別に,認定試験対策として即戦力になる書籍をご紹介します。
【目的別】認定試験の対策のオススメの本

(a)必ず用意しておきたい本
まず,点数表は必携です。検索しやすく解説も多い『診療点数早見表』がオススメです。
過去問対策としては,直近5回分の過去問とオリジナル問題を収録した『受験対策と予想問題集』が最適です。試験持込み資料として便利な付録「レセプト作成マニュアル」(算定とレセプト作成の要点を総まとめした冊子)も収録しています。
(b)学科の学習に適した本
学科の学習には,健康保険法や医療法といった,医療関連のあらゆる法制度の,①仕組みと内容,②医療機関での運用,③手続き・届出等の実務ノウハウ――をまとめた『医事関連法の完全知識』がオススメです。
(c)実技の学習に適した本
実技の学習には,診療報酬算定の入門書としては『入門・診療報酬の請求』が,点数と算定方法の早引きマニュアルとしては『診療報酬・完全攻略マニュアル』がオススメです。
また,レセプト作成の実技を学ぶには,実際の実技試験と同じ問題形式で解説を加えた『レセプト請求の全技術』が役立ちます。
(d)初心者の方にオススメの本
これから医療事務・診療報酬算定を学ぼうとする方には,各診療料ごとに,①学科問題,②点数算定問題,③レセプト記載問題,④レセプト完成問題――で構成されたドリル式の問題集『診療報酬・完全マスタードリル』がオススメです。
また,認定試験の前哨となる実践問題集としては,『医療事務【BASIC】問題集』をオススメします。
さいごに
診療報酬事務能力認定試験はとても難関な試験です。
しかし,合格すると医療事務として働く上で大きなメリットを手に入れることができます。
ぜひ挑戦してみましょう。
おまけ 合格者からのアドバイス




